2020年12月10日 10:12
皆さま、師走ですね。師走と言えば大掃除です。今年はなかなか難しい年でしたが、そんな困難さも払ってしまおうと、私たち教育普及係も、これまで引っ越ししてきたままになってきた資料やら、この1年でいらなくなってしまったものなどちょっと整理しようということなりました。資料室の奥やキャビネットの中を出し、いるものいらないものと分類していると・・・なんと、出てきました!1991年からの「夏休みこども美術館」のワークシートが!夏休みこども美術館は1990年から始まっているのですが、その頃は、教育専門の学芸員がおらず、さまざまな専門の学芸員たちが持ち回りで担当していたそうです。90年代の最初のころはまだ常設展示のリーフレットを転用してワークシートにしており、デザインもちょっぴりそっけないものですが、解説あり、クイズありと、それぞれ担当した学芸員が試行錯誤しながらワークシートを作っているようすが垣間見られます。
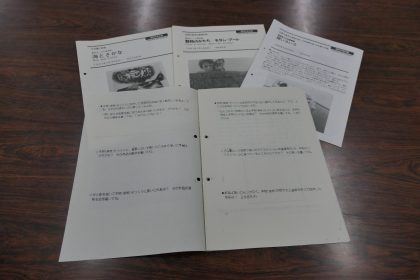
常設展示のリーフレットを転用した「夏休みこども美術館」のワークシート
1990年代半ばからは、ワークシートも豪華になり、カラー化。デザインも凝ったものになり、ちょっとしたお土産のような感覚のものに。正直、今のワークシートより、だんぜん紙も印刷もいいです・・・。だんだんと「夏休みこども美術館」に、学芸員たちが力を入れだしたことがわかります。それにしても、判型も内容も雰囲気も年ごとに違っていて、担当者の個性が爆発!していますね。

担当者の個性が爆発?なワークシートたち
そして、90年代末から教育専門学芸員が「夏休みこども美術館」を担当することになり、1999年から2007年まで「美術館蔵おじいさん」が登場して作品案内をするワークシートになりました。

「美術館蔵おじいさん」が作品紹介をするワークシート
実は、私、このワークシートを2007年まで担当しておりました。ついつい、ページをめくっては、まだまだ内容が練れてないなぁとか、この文章意外にいいな、など思ったり、あの時に一緒にワークショップをやった学生ボランティアさんはどうしているだろう?などと思い出したり・・・おっと、いけない!これでは大掃除がすすまない!
しかし、昔、「夏休みこども美術館」に来ていたこどもも、今はもしかしたら親として「夏休みこども美術館」に来ているのかもなぁ、など30年分のワークシートを見て感慨深く思いました。たまには大掃除もいいものです。
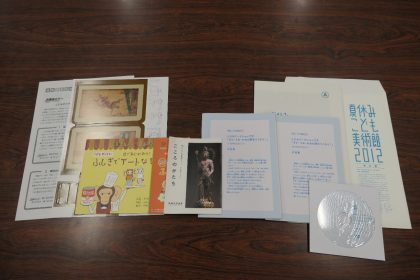
2000年代後半からまた判型がいろいろに。2012年にはワークシートではなく、記録集を作成しています
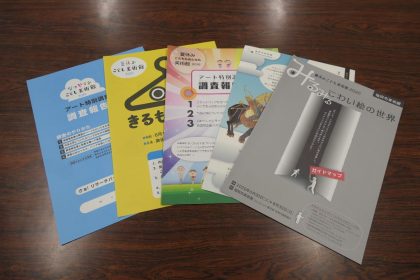
リニューアル直前からリニューアル後のワークシート
(主任学芸主事 鬼本佳代子)
2020年12月2日 17:12
先日、岡山県倉敷市にある倉敷芸術科学大学で開催されたゲリラ・ガールズの展覧会「『F』ワードの再解釈:フェミニズム!」を見てきました。ゲリラ・ガールズは、アメリカを拠点に美術業界における性差別や人種差別を告発する匿名のアーティスト集団。ゲリラ・ガールズの代表作ともいえる《女性がメトロポリタン美術館にはいるには、裸にならなきゃいけないの?》(1989、2005、2012年)は、メトロポリタン美術館の近代美術部門の展示状況を分析し、男女の非対称について告発する作品です。1989年版では「
ゲリラ・ガールズにならって、福岡市美術館の近現代美術の常設展示の状況を調べたことがあります。2014年度末、近現代美術室(現:近現代美術室C)内に展示されていた50点(50作家)中、作家の男女比は49:1(2%)、ヌードを描いた/表わした作品は12点、ヌードを描いた/表わした作品中の女性ヌードは12点(100%)でした。数字を出してみるとかなり衝撃的に感じます。
担当ではなかったとはいえ、出品作品についてコメントしてもよかったのかも…と今となっては思います。でも、テーマに合致した作品を選ぶとこうなってしまったこともよくわかるのです。
というのも、当時、約12000点の近現代美術コレクションに占める女性作家の割合は約4%、作品数は約2%だったからです。所蔵品にこれだけの不均衡があると、コレクション展示は所蔵品研究の成果でもあるので、どうしても展示内容にも影響してしまうのです。
あれから5年以上が経ちました。現在2階コレクション展示室で展開している「コレクションハイライト①②」にて展示中の43作家中6作家(13%)が女性であることからわかるとおり、非対称であることには違いないけれど、リニューアル前と比較すると徐々にわたしたちの意識も、状況も変わってきています。所蔵品にも、女性美術家の作品が毎年加わっています。今年度末発行予定の『研究紀要』では、福岡市美術館の活動をフェミニズムの観点から振り返り、2020年の最新状況を交えて報告しようと、ただいま準備しているところです。完成したら、ぜひご一読いただきたく思います。
さて、近現代美術室Bで開催中(12月27日まで)の「纏うわたし、見るわたし――やなぎみわとリサ・ミルロイ」は、女性アーティスト2人の当館所蔵作品を全点展示している展覧会です。展覧会を企画する動機はひとつではありませんが、背景には上記のような視点もありました。本展では女性の美術家による、着衣姿の女性あるいは衣服を表わした作品が並んでいるのです。

〔念のため付け加えておくと、ここで問題としたいのはあくまでも美術館の展示・所蔵作品における男女の不均衡であって、生物学的性の観点からなんらかの判断をくだそうとするものではありません。『フェミニズムはみんなのもの』(堀田碧訳、エトセトラブックス、2020年復刊)でベル・フックスはフェミニズムを次のように定義しています。「フェミニズムは、ひと言で言うなら、『性差別をなくし、性差別的な搾取や抑圧をなくす運動』のことだ」。問題は「差別」
(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)
2020年11月26日 15:11
「藤田嗣治と彼が愛した布たち」展が始まって、かれこれ…あら、もう会期があと3週間切れてる!?土日はあと3回しかありません。そろそろ、焦ってご予定を立てていただいて結構かと思います 笑。皆さまの御来館をお待ちしております。
展覧会を開催すると、マスコミ各社さんから取材をしていただくことがあります。取材時間も制作時間も限られているなかで、何かをつかもうとされるプロフェッショナルたちとの真剣勝負。皆さんの、ストックの広さ・深さ、そして瞬発力に、思ってもいなかったことを引き出してもらうことがあります。

今回、X新聞のZ記者の取材を受けました。Z記者は、質問するだけでなく、ご自分が感じたことも、正直に話してくれる方です。戦争画について、「今の目で批判するのは簡単。でも自分がその時生きていたら、きっと誰もがしたように行動したと思います。」と言われ、「わたしもそう思います」と返しました。「朝ドラ『エール』の主人公は、軍歌を作っていながら日本でサバイバルできたのに、どうして藤田はできなかったんでしょう。」という問いに「うーん。日本でのサバイバルにこだわらなくても、藤田には脱出先があった。これが大きいかもです。」と答えました。そう、藤田には日本以外のどこかに行く、という選択肢があった。非常に困難な道でしたが、それをやってのけた。だからこそ、「日本ではサバイバルできなかった」という事実が残ってしまったのでもありますが…。

戦争画のコーナーを過ぎ、藤田の手仕事コーナーにさしかかったとき、「藤田はできあいのものを、そのまま受け入れるのが嫌いでした。若い頃から、オリジナルなものを身に着けることに価値を見出して、手づくりをしていました。既製服を着るときも、ポケットをつけ足すなど、なにかカスタマイズして、自分のものにしないと満足しなかったみたいです。」ということを話しました。青年期から晩年まで、楽天的でめげない。難局を突破する。あらゆることに全力投球できる。時間を惜しんで制作に没頭する。衣食住すべてにわたって、自分の生活の隅々まで自分で作り上げる。そんな藤田像を話した時、Z記者が引き出してくれた言葉があります。
「藤田には生命力がある!」
「生命力」というキーワードは、藤田の作品や人となりに正面から向き合い、ストレートにご自分のことも語ってくださったZ記者との対話でなければ、きっと出て来なかったでしょう。藤田には、どんな環境下でも前に向かって進む力がありました。

藤田の手から生まれてくるすべて―絵画にも、針仕事にも、手紙にも―は、生命力にあふれています。この展覧会で、ぜひ、その力に触れに来てください。
(学芸課長 岩永悦子)