2022年1月20日 15:01
企画展「田部光子展『希望を捨てるわけにはいかない』」、1月5日に無事オープンしました。
展覧会のポスター・チラシが完成したとき、この美術館ブログに展覧会への意気込みや田部光子さんとのやり取りを書きました(「田部光子展のポスター」2021年10月28日)。
「任せた、好きにやっていいよ」と言われたものの、これまで十分に紹介されてこなかった作品や活動について調べる作業は、時に途方に暮れるものでもありました。展覧会出品歴も膨大で調査するたび増えていき、オーガナイザーとしての仕事、スペースの運営、エッセイの執筆等々、一人の仕事とは思えない幅広さと量に、どう整理したものかと頭を抱えたことも。加えてもちろん生活者として、つまり主婦、母としての仕事や画塾運営時には先生としての仕事もあった。田部さんは人と協働して事を起こすことが好きな人なので、家族や友人、周囲の協力もあるわけですが、それにしてもどうやれば両立できるのか今も不思議で仕方がありません。
本展覧会の準備期間はまさにコロナ禍。資料調査も思うように進まず、人に会うのも難しい状況でしたが、ぎりぎりまで粘って展覧会と図録ができました(図録はオンラインショップでも販売中です)。とはいえ現時点でわかっていないこと、もっと深く掘り下げなければと思うことも当然ながらあります。私も図録に比較的長い論考を書きましたが、それでも田部さんのすべてに言及できたとは考えていません、まったく。だからというわけではないですが、この展覧会が美術家・田部光子を広く知ってもらうだけでなく、田部光子研究がさらに展開するきっかけになればと願います(もちろん私もこれからも田部さんを追いかけます!)。田部光子をさらに知る糸口になればと、図録には田部さんが過去発表された文章もいくつか再録し、文献リストや年表には私が調べたものはほぼ全て載せています。今後新たな事実が付け加わったり、誤りは修正されていくでしょう。どの展覧会にも言える当たり前のことではありますが、あえて言わせてください。展覧会が開催されて終わり、ではなく、ここからまた始まるのだ、と。
田部さんは著書の中で、自身の作品が「百年早いのかもしれない」と述べておられます。その後に「ということは生きてる間もその後も夢を持てるということになる」と続くのがいかにも田部さんらしいと思います(「たった一人の旅鴉」『二千年の林檎 私の脱芸術論』西日本新聞社、2001年に収録)。
田部さんがこのように書いた後、2004年の熊本市現代美術館の依頼による代表作《人工胎盤》の再制作や、2005年に栃木県立美術館で開催された「前衛の女性1950-1975」への参加をきっかけに、〈九州派〉の一員としてではなく一人の美術家として、田部光子の活動に光が当たることになります。
しかしながら田部さんが2000年に「百年早いのかもしれない」と書いたのには理由があったはずです。確かに、田部さんの作品と活動を振り返ると、常に時代の先端を進んでいる(時には時代を随分と先取りしている)感があります。女性の社会における不平等からの解放を訴える《人工胎盤》(1961年)も、改革を訴えるはずのプラカード自体が旧態依然のままだと気づき、権力に対抗する名もなき人々への共感とともに作りあげた《プラカード》(1961年)も、1960年代末に「記録映画家」として反芸術パフォーマーたちの姿を映像に収めていたことも、1970年頃表現と猥褻の問題に画家として果敢に挑戦していたことも、既存の団体や公募展のオルタナティブとしてだけでなく女性たちの居場所にもなりうるグループとして構想し立ち上げた〈九州女流画家展〉(1974~1984年)も、女性の手による新たな女性表象と言える1970~80年代の絵画群も、1988年の「主婦定年退職宣言」も、あるいは1995年から福岡市美術連盟理事長として行なってきた活動も、1990年代そして2000年代以降の作品も、2015年に開設したオルタナティブスペースとも呼べる「TMT・ART・PROJECT 3丁目芸術学校」も。
2022年の今、展覧会開幕から約2週間が経って実感するのは、たくさんの人が田部光子の作品や活動に関心を持ち、アクチュアルなものとして受けとめているということです。展覧会への反応を見聞きする限りではありますが、田部さんの作品と活動に刺激を受けている人が既にたくさんいます。「百年」より早く、「その後」よりずっと前に、私たちはあなたに追いつくことができるかもしれません!田部さん!
最後に。初期から最近作までの田部光子作品の造形力や表現力も、本展覧会で知っていただきたいことです。開幕日の前日、美術専門の作業員の方々と一緒に展示作業をしていた私は、「展示がうまくいくだろうか」という極度の緊張と不安の中にいました。しかし作品が会場に並びはじめると、田部さんの作品の圧倒的な力に痺れ、興奮し、気づいたときには不安は払拭され、「何を心配していたんだろう、こんな素晴らしい作品が並ぶのだからいい展示にならないわけがない」と思うようになっていました。この感覚をみなさまと共有できるかもしれないことにもわくわくします。ぜひ会場で、田部光子作品の力、美術の力を目撃そして体感してください!

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景
(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)
2021年6月16日 09:06

先日閉幕した企画展「ソシエテ・イルフは前進する 福岡の前衛写真と絵画」(以下「イルフ展」)(2021年1月5日~3月21日)では、会期中に2回の記念講演会を開催しました。登壇者には近現代写真の専門家であるお二人のゲスト(名古屋市美術館学芸員の竹葉丈氏、インディペンデントキュレーター[現・東京ステーションギャラリー学芸員]の若山満大氏)をお招きしました。2回の講演はいずれもイルフの活動した1930~40年代の写真家たちが向き合っていた時代状況や複雑な立場を明らかにする内容で、イルフ展で紹介した作品・資料への理解を更に深められるものでした。ここに、担当者による講演会のレポートをお届けします。前回の竹葉氏の講演会に引き続き、今日は、若山氏の講演会のレポートです。
「趣味と報国:ソシエテ・イルフをもっとよく知るための写真史 1920-1942」(登壇者:若山満大氏、開催日:2021年3月6日14:00~15:30、会場:ミュージアムホール)
若山氏には、アマチュア写真家が台頭する明治中期から戦時下にかけて、つまり1880年代末から1940年代までの半世紀の写真史を、幅広い事例や資料とともにお話いただきました。各時代における表現様式の変化や写真家たちの活動はイルフの活動とリンクしており、イルフのメンバーが時代と社会の状況に呼応しながら活動していたことが見えてきました。
冒頭では、国内の写真団体・写真愛好家にどのような特色があり、それがどのように変遷していくかをお話しいただきました。明治中頃の写真団体は、写真師・旧華族・お雇い外国人などの富裕層に限られていたようです。初期の写真愛好家たちの関心は、夜に鮮やかな写真を撮る手法、大判写真を撮る手法の研究など技術面にあり、その後変化していきます。1893年に開催された「外国写真展覧会」の出品作は、明確な主題、前景・後景の被写体の写し方、セピア色の諧調など、“オーソドックスな風景画”のような作品です。海外の作例からの影響を受け、日本の写真愛好家たちも絵画を模範とする写真表現に取り組むようになりました。
1910年代から1920年代にかけて、写真愛好家の裾野は広がっていきます。この変化には、雑誌を通し情報が地方都市にも届くようになったこと、第一次世界大戦後の経済の動きによってカメラや写真材料が富裕層でなくとも買えるようになったこと、新聞社がメディアイベントを開催する機運が生まれたことなどが複雑に絡み合っています。1926年-1927年刊行の『日本写真年鑑』に掲載されている地方のアマチュア写真団体は476団体、加盟者は13889名に上りました。イルフメンバーの田中善徳が所属していた「福岡白光会」も掲載されていました。
写真趣味が流行する中で、アマチュア写真家の中から雑誌編集に携わったり、投稿作品を審査したりする、特別な地位の人々が登場します。講演の中で例に挙がったのは1921年に写真芸術社を主催した、福原信三です。福原は「写真とは光と影のグラデーションである」「自然から受け取った情感を写し取るものだ」といった写真観を発信していました。若山氏は、ヒエラルキーの上部にいたオピニオンリーダーも重要だが、写真産業を作り上げその権威を下支えしていたのはフォロワーたちであるという点を指摘しました。お話を聞きながら思い出したのは、1930年代にイルフメンバーの高橋渡が安易なアマチュアリズムに抵抗し始めたことです。カメラ雑誌に論考を発表し、存在感を表し始めていた高橋は、アマチュア写真界のヒエラルキーを地方から突き崩す狙いがあったのでしょうか。
1930年代は、雑誌『光画』を嚆矢として、新興写真と言われる新たな傾向の写真が登場します。カメラに特有の現象であるブレによる表現や、レンズを通して何気ない風景に新しい視線を投じた作例など、作品のスライドを見ながら、移り変わる表現傾向を確認しました。新興写真がシュルレアリスムの傾向を持つ前衛写真へと進化していく過程として、ナゴヤ・フォトアヴァンガルド、前衛写真協会、丹平写真倶楽部の作家たちと共にイルフメンバーの作例が紹介されました。
講演の終盤は、戦時下の写真家の動きにフォーカスします。この頃、スパイを防ぐためという理由で撮影場所やアングルが限定され、写真材料が配給制になるなど、アマチュア写真を巡る状況が厳しくなっていきます。限られた資源を戦争のために費やすべきという風潮が強まる中で写真家の活動は制限され、社会に有用である、と認められなければ趣味としての写真を続けることができなくなっていきました。戦時下で許された写真の例が、報道写真です。戦場や植民地を捉えた写真は国威発揚の効果を持ち、対外・国内宣伝のための雑誌に掲載されました。しかし、大多数のアマチュア写真愛好家たちにとって戦地に赴くことは難しく、写真を続けるためのなんらかの「方便」を見つける必要に迫られていたのでした。
こうした状況の中、アマチュアの写真家たちが選び得た“前向きな妥協案”として若山氏が挙げたのが、民俗学的な写真と慰問写真です。民俗学的な写真とは、国内の伝統的な暮らしが残る集落や風土を主題とした写真のことで、濱谷浩の仕事などが挙げられます。郷土を撮影することは当時でいう民族意識の高揚につながり、銃後の暮らしを鼓舞する“草の根の報道写真”としての意味合いを持ちました。
慰問写真とは、戦地の兵士に向けて送られた、故郷の家族を写した写真のことです。慰問写真は、家族は無事だというメッセージとともに、それを手に取った兵士に前線を守り、家族を守るために戦わなければならないことを伝える「督戦装置」としても機能しました。写真家たちは、慰問写真のカメラマンに名乗り出ることで、物資統制の最中において貴重なフィルムや撮影の機会を得ることができたのでした。
ソシエテ・イルフのメンバーは1920年代頃から写真に傾倒し、グループ結成当初は前衛であることを掲げて同人誌や作品制作を行っていましたが、1940年頃に各々の活動の傾向が変化し、熊本・五箇荘の集落や柳川などを主題にした、民俗学的なアプローチの写真を撮るようになります。これは単なる志向の変化だけではなく、当時趣味として写真を撮り続けるための必然的な選択だったのかもしれません。
半世紀にわたる近代写真史を振り返ると、愛好家たちが地方で活動し始める時期、写真専門雑誌のなかでアマチュア写真家たちが活躍し始める時期、そして戦時下の文化統制の中で写真の有用性をアピールすることが求められた時代と、各時代の動向にイルフの活動がリンクしていることが感じられました。具体的な写真技法や時代状況の解説から、一枚の写真に時代ごとの表現動向と社会史が折りたたまれていることが分かる講演会でした。
(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ)
2021年5月26日 17:05
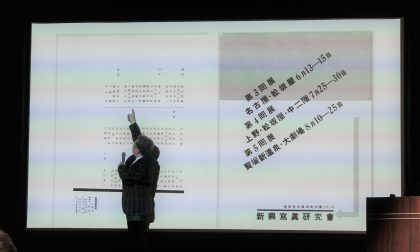
先日閉幕した企画展「ソシエテ・イルフは前進する 福岡の前衛写真と絵画」(以下「イルフ展」)(2021年1月5日~3月21日)では、会期中に2回の記念講演会を開催しました。登壇者には近現代写真の専門家であるお二人のゲスト(名古屋市美術館学芸員の竹葉丈氏、インディペンデントキュレーター[現・東京ステーションギャラリー学芸員]の若山満大氏)をお招きしました。2回の講演はいずれもイルフの活動した1930~40年代の写真家たちが向き合っていた時代状況や複雑な立場を明らかにする内容で、イルフ展で紹介した作品・資料への理解を更に深められるものでした。ここに、担当者による講演会のレポートをお届けします。
「前衛写真(フォト・アヴァンギャルド)の行方―<ソシエテ・イルフ>を巡る写真家たち」(登壇者:竹葉丈氏、開催日:2021年2月27日14:00~15:30、会場:ミュージアムホール)
近現代写真史をご専門として数多くの展覧会を担当されてきた竹葉氏には、名古屋の前衛写真家・坂田稔(1902-1974)を中心に、前衛写真運動の展開についてお話しいただきました。「イルフ展」の会場でも紹介したように、坂田は福岡に3日間滞在し、ソシエテ・イルフのメンバーと交流し、写真観を巡って論争しました。当初「坂田VSイルフ」という構図の実態についてのお話をお伺いできるのではと考えていましたが、坂田研究の第一人者である竹葉氏からは、より踏み込んだ見解をお伺いする事ができました。
まずご紹介いただいたのは、「新興写真」の定義やその実践の場についてです。新興写真とは、1930年代初頭に欧米から日本に紹介されて流行した写真表現のことです。この頃の写真愛好家たちはカメラが持つ機械的な特性に目を向けるようになります。時代や生活の記録、主観を排し現実を直接的に切り取ったイメージ、レンズと光の作用を用いた造形表現、など、写真表現はこれまでとは違う幅広い展開を見せました。その実践の場もまた、展覧会、地元志向の写真雑誌、地域産業の振興を目的とした催しと様々です。名古屋では「20万」とも謳われたほどカメラを持つ人々が増え、一方で、それまでの“旦那衆”の集まりであった写真倶楽部は衰退して行きます。作品の出来映えではなく、「写っていれば良い」とするアマチュアに対して、現像や焼き付け等の技術的サービスを行う「写真技術の店」なるものが隆盛し、やがて地元写真愛好家に向けた雑誌や、文化サロンの役割を果たして行きます。一方、福岡では「地域産業の振興」を動機として新興写真が流行しました。そのことを示す資料が、「イルフ展」で展示していた1937年刊行の『新興写真選集』(福岡日日新聞)です。九州の写真愛好家による福岡の特産品・観光名所などをテーマにした新興写真が収録されたこの写真集は、大都市の新興写真の展覧会や雑誌の開催・発行年数から遅れたとは言え、「新興写真」が目指した写真の機能が地域から発信、活用された事例として大変興味深い資料だと竹葉氏は指摘しました。
名古屋で写真材料店「ジャパン・コダック・ワァク社」を営んでいた写真家・坂田稔はこうした状況下で活躍し、やがて1939年2月、「ナゴヤ・フォトアヴァンガルド」の中心メンバーとして前衛写真運動をけん引しました。講演の後半は、そんな「坂田の行方」を軸に進んでいきました。
講演の中で竹葉氏は、1939年頃の坂田が“前衛写真を宣言すること”を巡って一見矛盾するような発言をとっていることを示しました。アマチュアが前衛写真という言葉を安易に口にすることを警戒しながら、「前衛芸術とは、予想する文化的将来に合致せしむるよう現在の芸術としてさらに前進せしめんがための一切の芸術行動」と宣言していること。前衛写真という言葉の使用を「自粛したい」と言ったかと思えば、アルフレッド・バー・Jrによる「モダンアートの系譜図」を翻訳して雑誌に掲載し、前衛美術の流れの中に自分たちの写真を位置づけようとしていたこと。これらの坂田の言動は、彼の周囲の写真愛好家たちを戸惑わせたことでしょう。
竹葉氏はこの状況を解釈して「この時期に日中戦争の拡大に伴い、報道写真が台頭、注目される中で、前衛写真という言葉とその機能が消される。趣味でやっているだけじゃないかと言われることが怖かったのでしょう」と述べました。当時の文化統制の中で、前衛を冠した美術団体や展覧会は不穏だといって検閲される事例が少なくありませんでした。坂田は必要に応じて「前衛」を大っぴらに語れる場面とそうでない場面を察知し、使い分けていたのかもしれません。
1939年10月14日から16日まで坂田は福岡に三日間滞在してイルフのメンバーと過ごした後、11月にナゴヤ・フォトアヴァンガルドを解散します。竹葉氏は、「この間のことは未だによく分からないが、やはり坂田にとっては、福岡のソシエテ・イルフのメンバーの方が名古屋のメンバーより話が合ったのでは?」と推測します。実際、この頃の坂田とイルフのメンバーの写真の傾向には近いものがあります。イルフが解消した1940年に顕著なのですが、高橋渡や久野久、許斐儀一郎の作品には、民家の壁や建築部材、伝統的な暮らしを営む集落を主題にしたものがあります。同時期に坂田は柳田国男が提唱した「常民」をテーマとした民俗学に接近、この頃に農家の土壁や障子、海鼠壁などを「日本建築の美」が現れた被写体として取り上げていました。「前衛写真が挫折/転向してある程度の成果を見せたかどうかは検討の余地がある。彼らは民家・民藝を撮影した方法で抽象美術の方向を進むことを坂田は信じてやまなかった」。以上の竹葉氏の解釈は、イルフにも当てはまるのかもしれません。
本講演会で語られた内容は、前衛写真に関わった者が戦時体制の中で挫折/転向したときにどのような表現に変容していくか、という問題に踏み込んだものでした。お話を伺うと、坂田が「前衛」を巡って自らの針路と態度を決めかねていた時期に出会い、夜通し写真論を交わしたイルフのメンバーは彼と何らかのヴィジョンを共有していたのではないか、とも思わせられます。イルフが置かれていた状況を多角的に捉える機会となる、貴重な講演でした。
(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ)